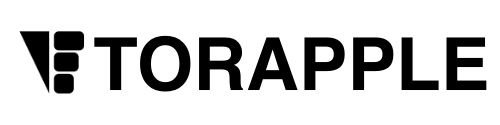マラソンやトレイルラン・トライアスロン・1500m競泳など、3分以上持続してパワーを出し続ける持久系スポーツに取り組む人にとって、「スタミナ切れ」を起こさないと言うのは大きなテーマですね。
日常生活でも、なんとなく元気がない状態を指して「スタミナ不足」と表現します。
また「スタミナをアップに焼肉を食べよう」と、ガッツリ食べると言う人も。
ですが、そもそも持久系スポーツにおけるスタミナ不足とは、どのような状態のことでしょう?
また、スタミナが切れないようにするのには「ガッツリ食べる」ことは大切かも知れませんが、重要なのは「何をガッツリ食べるのか?」です。
ここでは、マラソンなどのレースやそれに向けたトレーニングのクオリティをあげるための「スタミナ」とは何かを知った上で、スタミナを枯渇させない栄養摂取について考えます。
しっかりトレーニングを積んでいるのにタイムが伸びない、レース途中でバテる事に悩んでいる方は参考にどうぞ。
スタミナ切れの原因と症状
運動時の主なエネルギー源は、筋肉の中に貯蔵された「グリコーゲン」です。
食べ物から摂取した糖質は、身体の中で肝臓と骨格筋に「グリコーゲン」と言う形で貯蔵されます。
これが、運動時のエネルギー源として利用されます。
高カロリーを必要とする、レース時間が1時間を超えるような持久型のスポーツでは、このグリコーゲンが枯渇することで、スタミナ切れを引き起こします。
フルマラソンでよく言う「30kmの壁」は、レース後半で生じるグリコーゲンの減少や枯渇が原因です。
グリコーゲンの貯蔵量は、競技成績に大きな影響を及ぼすのです。
そして、スタミナ切れを引き起こすもう一つの重大な原因は貧血です。
貧血というと、か弱い女性がなるものというイメージかもしれませんが、スポーツに伴う貧血があることを知っておきましょう。
マラソンなどの有酸素運動では、全身の細胞に酸素を運搬するヘモグロビン、運動によって筋肉中の酸素濃度が低下した時に酸素を放出するミオグロビン、体内に発生する活性酸素を分解する酵素(カタラーゼ)などの必要量が増します。
これらの物質は「鉄」を材料としているので、鉄が不足すると鉄欠乏性貧血を起こし、持久力の低下を引き起こすのです。
また激しいトレーニングを行うと、赤血球の破壊や筋組織の破壊によって鉄の消費量が増え、貧血を起こしやすくなります。
マラソンのように長時間走り続けることで、足底に衝撃が繰り返されると、溶血性の貧血を生じることもあります。
大量に汗をかくことで、鉄分が損失することも貧血を生じさせる一因になります。
特に女性の場合は、月経の際に1日当たりおよそ0.5㎎の鉄が失われるので、意識的な鉄分の摂取が重要です。
スタミナ切れを起こさないためには、万全な貧血対策が必要なのです。
スタミナと糖質
スタミナと糖質の関係についてもう少し詳しく見ておきましょう。
運動時は、筋肉中でブドウ糖がエネルギー源として使われます。
食べ物から摂取した糖が不足すると、筋肉中に蓄えてあったグリコーゲンがエネルギー源として利用されます。
運動強度が高くなる、あるいは低強度でも運動時間が長くなると、筋肉の中に貯蔵されたグリコーゲンが消費されます。
体重60kg、体脂肪率15%の一般成人男性の場合、脂肪は約65000kcal程度貯蔵できます。
それに対し、骨格筋の中に貯蔵することができるグリコーゲンは1500kcal程度。
大量に貯蔵できる脂肪と違い、グリコーゲンを筋肉中に蓄えておくには限界があります。
だからこそ、グリコーゲンを可能な限り十分に蓄えた状態で運動を開始する必要があります。
また、運動後はグリコーゲンを回復させるのに十分な糖質を摂取しなければいけません。
練習やレースで消費したグリコーゲンは可能な限り早く回復させることが大切です。
個々人の体格で糖質の必要量は変わりますが、一日に体重1kgあたり7g以上を目安に糖質を摂取しましょう。
例
体重60kgなら1日あたり420gの糖質が必要です。
ご飯茶碗1杯およそ150g中の糖質量は55.7gです。
420gの糖質を摂取するにはご飯7.5杯分が必要です。
糖質を効果的に摂取するためにはビタミンが必要
ご飯などの糖質を摂取するときは、ビタミンB1を一緒に摂るようにしましょう。
ビタミンB1は、糖質を含む食べ物をエネルギーにするために必要です。
これが不足すると糖質がエネルギーにならないばかりか、ピルビン酸という疲労物質として体内にたまってしまい、その結果疲れやすくなるのです。
糖質を十分に摂っているのに疲れやすいという人は、ビタミンB1の摂取を心がけましょう。
白米よりも、胚芽米や玄米、全粒粉のパンなど未精製の穀類にビタミンB1は多く含まれます。
日常の栄養摂取では、こうした未精製の穀類を選ぶと良いでしょう。
試合でバテないためのグリコーゲン・ローディング
試合の前には、グリコーゲンを戦略的に摂取しておきましょう。
糖質の高い食事を摂ってグリコーゲンを体内に蓄えることを「グリコーゲンローディング」と言います。
前述したようにグリコーゲンは、肝臓と骨格筋に蓄えられます。
肝臓に蓄えられたグリコーゲンは血糖の維持に、筋肉に蓄えられたグリコーゲンは運動のエネルギー源になります。
グリコーゲンローディングは通常7日間かけて行います。
ローディングスケジュール
1日目は、糖質を使い果たす運動を行います。
2日目から4日目までは運動量を少なくして、適度に糖質を含むバランスの良い食事を行います。
5日目から7日目、運動は少なく、高糖質の食事を行います。
そして8日目が試合。
高糖質の食事とは、1日の摂取エネルギーの70%を糖質で摂取し、脂質は15%以下、たんぱく質は15%程度という配分です。
糖質を増やす分、脂質は減らしますが、たんぱく質は通常の食事同様に摂取しましょう。
また、ビタミンやミネラルの摂取量が減ってしまうとだるさや疲労を引き起こすので、野菜や海藻、果物をしっかり摂取するように心がけましょう。
試合当日の糖質摂取のタイミング
試合当日も高糖質の食事を行います。
ただし試合開始時間を考慮して、試合の3~4時間前までに食事を摂取します。
また、糖質の摂取量が足りない場合は、試合前にグリセミックインデックスが高く吸収が素早いフルーツジュースやバナナ、市販のゼリー飲料などでグリコーゲンの補給を行うと良いでしょう。
しかし、注意も必要です。
運動開始30分くらい前に大量の糖を摂取すると、運動開始とともに血糖値が下がってしまう運動誘発性低血糖が起こることがあります。
これを予防するには、運動開始の1〜1時間半前に糖質を摂取して、血糖値が安定してから運動を開始するように心がけるようにします。
スポーツ貧血対策のための食べ物選び
貧血対策には、鉄を多く含む食品を摂取しましょう。
ここで押さえておきたいのは、鉄分のタイプです。
食品中に含まれる鉄分は、肉や魚などの動物性食品に多く含まれるヘム鉄と、小松菜やホウレンソウ、大根の葉など植物性食品に多く含まれる非ヘム鉄があります。
ヘム鉄は非ヘム鉄よりも吸収効率が良いというメリットがあります。
一方非ヘム鉄は吸収効率が劣りますが、鉄臭さがないというメリットがあります。
また、一工夫で吸収効率を高めることもできます。
非ヘム鉄を摂るときの工夫は、ビタミンCを多く含むものと一緒に摂ることです。
ビタミンCの多いイチゴや柑橘類などのフルーツを食後に食べたり、ピーマンやパプリカ、ブロッコリーなどと組み合わせたり、レモンを使いビタミン Cタップリのドレッシングやソースとともに食べるのもおすすめです。
注意したいのは、お茶やコーヒーに含まれるタンニンです。
タンニンは、鉄の吸収を阻害します。
そのため、食事中や食後すぐに飲むのは控える方が良いでしょう。
発汗で失われる鉄分を考慮して運動前の食事で鉄分をしっかりと摂取しましょう。
小松菜とレモンなどを組み合わせて、鉄分の吸収効率を考慮したスムージーを食事に添えるのも良いですね。
蜂蜜など、グリセミックインデックスの低い糖類をプラスすると、エネルギーの補給にもなり一石二鳥です。
スタミナ切れの対策まとめ
スタミナをつけるには、糖質の枯渇を防ぎ、鉄分を多く含む食事を摂ることが重要です。
またレースや試合前には、グリコーゲンローディングを行い、戦略的にグリコーゲンを体に貯蔵しておくと良いでしょう。
ただしグリコーゲンローディングは、大切な試合の時にいきなり実施せずに、一度リハーサルをして見ることをおすすめします。
もちろん、スタミナアップには持久的トレーニングを積むことが大切です。
持久的トレーニングを積んだ人は、運動時の糖質利用が減り、体内に多量に存在する脂質の利用が増えることがわかっています。
つまり、糖質が枯渇しない、スタミナのある体質になるということですね。
持久的トレーニングと栄養摂取、両方のアプローチで、スタミナ切れを起こさないフィジカルを作りあげていきましょう。