PR
基礎代謝・総消費エネルギー・カロリー収支理論の解説と使い方の例
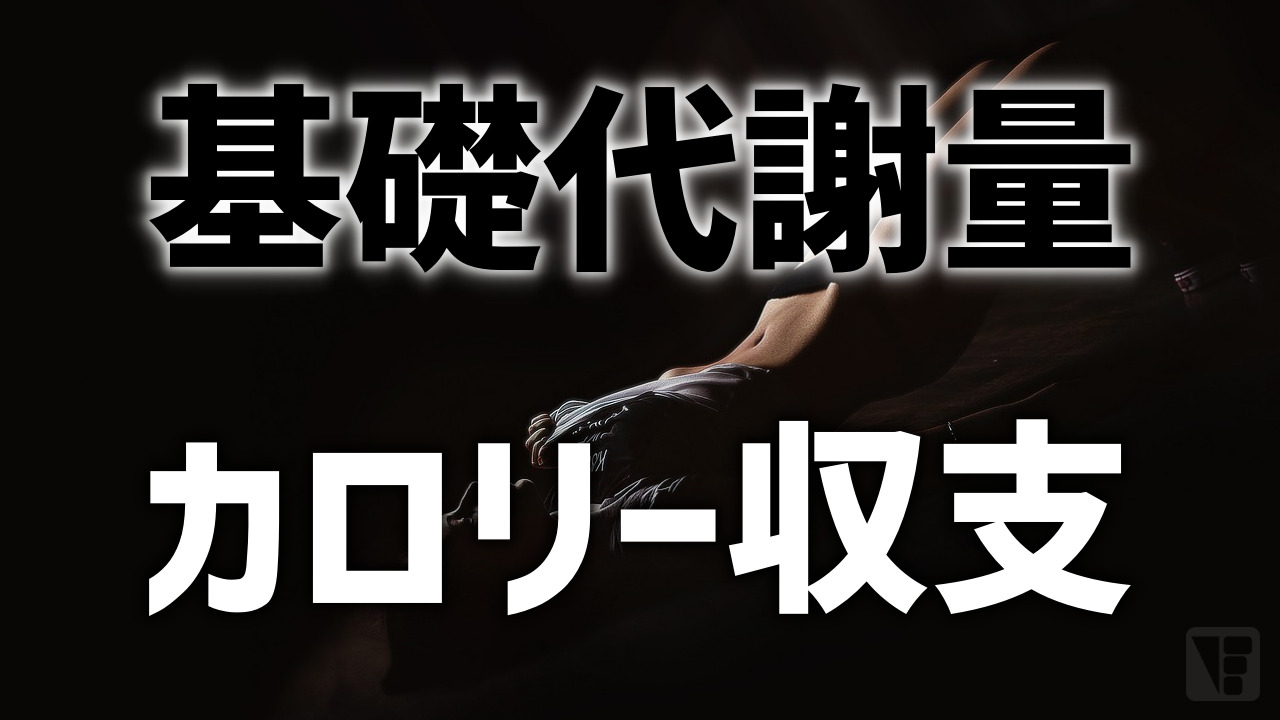
筋トレでもダイエットでもボディメイクするために必要なのがカロリー収支です。
自身の基礎代謝量と総消費カロリーを基準として、カロリー収支バランスがプラスになるかマイナスになるかをコントロールすることで体重を増やしたり部屋したりできます。
逆にカロリー収支理論を知らなければ「たまたま太った」「たまたま痩せた」を繰り返すだけで、自分で自分の体型をコントロールすることができません。
このページでは基礎代謝量と総消費カロリーの算出方法と、カロリー収支の使い方の例をまとめています。
ダイエット方法を1000個知るよりもカロリー収支の理論1つを理解する方が大事です。一度理解してしまえば、ほぼ一生役に立つ知識なので是非ご確認ください。
計算ツールはこちら
基礎代謝 BMR
基礎代謝量とは
生命維持に必要な代謝(エネルギー)。つまり「生きているだけで使ってしまうエネルギー」のこと。
BMR:Basal metabolic rate
生命維持、つまり心臓や脳みそなどの内蔵を動かしたり息をしたりしているだけで1日に消費されるエネルギーのことです。
基礎代謝は年齢・性別・体重・個人の体質などで差がでますが、大まかな数値は次のようになります。
| 年齢 | 参照体重 (男性) | 基礎代謝 (男性) | 参照体重 (女性) | 基礎代謝 (女性) |
|---|---|---|---|---|
| 15-17 | 59.7 | 1,610 | 51.9 | 1,310 |
| 18-29 | 64.5 | 1,530 | 50.3 | 1,110 |
| 30-49 | 68.1 | 1,530 | 53.0 | 1,160 |
| 50-64 | 68.0 | 1,480 | 53.8 | 1,110 |
| 65-74 | 65.0 | 1,480 | 52.1 | 1,080 |
ざっくりですが、標準体型の人であれば「男性は約1500kcal前後」「女性は1200kcal前後」と考えて良いです。
体型が大きかったり筋肉量が多い人は標準よりプラス、小柄な人や筋肉量が少なければ標準より数字が小さくなると考えてください。
総消費カロリー TDEE
総消費カロリーとは
「基礎代謝」と「活動代謝」の合計。活動代謝は生活活動に必要な代謝(エネルギー)。つまり「仕事や遊びなど、活動するために必要なエネルギー」のこと。
TDEE:Total Daily Energy Expenditure
「何もしなくても生きてるだけで消費されるカロリー」に「運動したり活動して消費したカロリー」を加えたものが、1日のトータルの消費カロリー(総消費カロリー)です。
活動代謝は普段の生活習慣によって差がでます。肉体労働を仕事としている人や定期的な運動習慣がある人は活動代謝が高くなり、デスクワークメインの人などは活動代謝が少なくなります。
個人個人で数字は異なるので一概に決めつけることはできませんが、おおまかな目安として身体活動レベル(厚労省)の係数が定められています。
| 身体活動 レベル | 日常生活の内容 |
|---|---|
| 低い 1.50 | 生活の大部分が座位で、 静的な活動が中心の場合 |
| ふつう 1.75 | 座位中心の仕事だが、職場内での移動や 立位での作業・接客等、通勤・買い物での歩行、 家事、軽いスポーツ、のいずれかを含む場合 |
| 高い 2.00 | 移動や立位の多い仕事への従事者、 あるいは、スポーツ等余暇における活発な 運動習慣を持っている場合 |
「基礎代謝」に「身体活動レベルの係数」をかけると、おおまかな「総消費カロリー」が出るという具合です。
例:30歳男性標準体型
- 基礎代謝=約1,530kcal
- 身体活動レベル低い=係数1.50
- 総消費カロリー=1,530×1.50=約2295kcal
1日に消費するカロリーはだいたい2295kcalくらい
基礎代謝・総消費カロリーの計算方法
基礎代謝・総消費カロリーを個人に合わせて計算する式がいくつか存在します。より正確に参考値を出したい人は利用しても良いです。
ただ、いずれの式も「推測値」なのであくまでも参考する程度にしてください。
ハリス・ベネディクト(改良版)
男性:88.362+(13.397×体重kg)+(4.799×身長cm)−(5.677×年齢)
女性:447.593+(9.247×体重kg)+(3.098×身長cm)−(4.33×年齢)
ハリス・ベネディクト(日本人改良版)
男性:66.4730+13.7516×体重kg+5.0033×身長cm-6.7550×年齢
女性:655.0955+9.5634×体重kg+1.8496×身長cm-4.6756×年齢
国立健康・栄養研究所の式(Ganpuleの式)
男性:(0.0481×体重kg+0.0234×身長cm-0.0138×年齢-0.4235)×1,000/4.186
女性:(0.0481×体重kg+0.0234×身長cm-0.0138×年齢-0.9708)×1,000/4.186
国立健康・栄養研究所の式(2007)
((0.1238+(0.0481×体重kg)+(0.0234×身長cm)-(0.0138×年齢)-性別*1))×1000/4.186
男性=0.5473×1
女性=0.5473×2
Schofield の式
18-29歳男性:(0.063×W+2.896)×1,000/4.186
18-29歳女性:(0.062×W+2.036)×1,000/4.186
30-59歳男性:(0.048×W+3.653)×1,000/4.186
30-59歳女性:(0.034×W+3.538)×1,000/4.186
60歳以上男性:(0.049×W+2.459)×1,000/4.186
60歳以上女性:(0.038×W+2.755)×1,000/4.186
W:体重(kg)、H:身長(cm)、A:年齢(歳)
FAO/WHO/UNUの式
18-29歳男性:(64.4×W-113.0×H/100+3,000)/4.186
18-29歳女性:(55.6×W+1,397.4×H/100+148)/4.186
30-59歳男性:(47.2×W+66.9×H/100+3,769)/4.186
30-59歳女性:(36.4×W+104.6×H/100+3,619)/4.186
60歳以上男性:(36.8×W+4,719.5×H/100-4,481)/4.186
60歳以上女性:(38.5×W+2,665.2×H/100-1,264)/4.186
W:体重(kg)、H:身長(cm)、A:年齢(歳)
The Mifflin, M. D., St Jeor formula
男性:10×体重(kg)+6.25×身長(cm)−5×年齢+5
女性:10×体重(kg)+6.25×身長(cm)−5×年齢−161
国立スポーツ科学センター(JISS)
基礎代謝量=28.5×除脂肪体重
除脂肪体重=体重-脂肪量
脂肪量=体重×体脂肪率
Katch-McArdle式
370 + (21.6 × 除脂肪体重 kg)
どの計算式も「推定値を出すもの」であって目安にしかなりません。重要なのは、その数値を目安にカロリーコントロールをした結果です。
例えば
総消費カロリーが2000kcalの人が、1日1800kcalで1ヶ月生活してみた
- 1800kcalで生活したら痩せた
- 1800kcalで生活しても体重の増減がなかった
- 1800kcalで生活したら太った
これがあなたにとって「本来必要なデータ」です。自分専用のデータが取れたら、もう計算式で出した数字は必要ありません。
基礎代謝量の計算は「まだ基準となる数字を持っていない人が参考にするだけ」なので、計算して何キロカロリーになろうがどうでもいいのです。
計算ツールを作ったので興味ある人だけご利用下さい。
国立健康・栄養研究所の式の計算ツール
カロリー収支(エネルギー収支バランス)
現代において筋トレやダイエットにおける基準として使われている理論です。
カロリー収支の式
カロリー収支=(摂取カロリー)ー(総消費カロリー)
「摂取するカロリー」と「消費するカロリー」の差分をカロリー収支と言います。厚労省では「エネルギー収支バランス」と呼ばれていますが同じ意味です。
カロリー収支の理論
- カロリー収支がプラスなら体重増加↑
- カロリー収支がマイナスなら体重減少↓
摂取カロリーの方が多ければ余ったエネルギーのぶん体重が増え、逆に消費カロリーの方が多ければ不足したカロリーぶん体重が減少するという考えです。
体重とは「筋肉」「脂肪」どちらも含みます。トレーニング内容や摂取カロリーの内訳(PFCバランス)によって、筋肉が増減するのか、脂肪が増減するのかが変化すると思って下さい。
筋肉を増やしたければカロリー収支がプラスになるように食事管理をして、ダイエットしたければカロリー収支がマイナスになるようにコントロールすることになります。
基礎代謝・総消費カロリーの管理方法
管理アプリ
基礎代謝の目安を知ったら、それを基準として日々の摂取カロリーをコントロールするのが重要。
メモに残しても、エクセルで管理してもなんでもいいので、あとで「○○kcalで生活したら、結果どうなったか」を振り返られるようにします。
アプリが一番便利です。
人気で王道のアプリ
栄養士から応援メッセージが欲しい人用
記録の重要性と必要性
記録するのは「原因」と「結果」です。
記録する内容
- カロリー収支とPFCバランス(原因)
- 体重や見た目の変化(結果)
- トレーニング記録(必要であれば)
失敗が成功のもとになるためには「失敗した原因が分かる」ことが重要。 原因がわかれば修正すればいいだけです。
ダイエットで有りがちなのが「結果」ばかり見てしまうこと。つまり、「体重が減った or 増えた」だけを見て一喜一憂してるのが問題です。
記録してないから、何回ダイエットしても失敗を繰り返してしまいます。
記録するコツ
記録のポイント2つ
- 摂取するカロリーを決めること
- 決めたルールを守ること
これで基準が作られます。
まずダイエットのために目標とするカロリー摂取量を決めます。ただ、最初に計算して出す数字は、あくまでも予測で「このカロリー摂取量であれば痩せるであろう」という推測値です。
そして決めたカロリー摂取量(カロリー収支)を守ります。出来れば1ヶ月、少なくとも2週間は結果が出るまでルールに従って生活します。
記録をみてカロリー収支の調整
例えば目標とする摂取カロリーが1200kcalだったとします。1ヶ月後の体重の変化によって修正方法を変えます。
体重が減った場合
結果が目標通りに進んでますので計画が正しかったことがわかります。そのまま1200kcalを継続して良いでしょう。
ただ、体重が変化することで基礎代謝量が変わりますので、2週間〜1ヶ月ごとに計算し直しても良いと思います。
体重が減らなかった場合
おめでとうございます。
これで次の1ヶ月間で100%痩せられる方法を手に入れることが出来ました。「1200kcalだと痩せない」という完全にあなただけのオリジナルのデータです。
- 原因:1200kcal/日
- 結果:痩せない
1200kcalを基準として、摂取カロリーを減らす(1100kcalにするなど)か、運動して消費カロリーを増やすか。どちらでもかまいませんので好きな方法を選んでください。これで100%痩せます。
基礎代謝・カロリー収支の使い方の例
あくまでも目安ですが、ダイエットする時のカロリー収支の使い方の例をとして、参考までの期間と数値を出してみます。
既にダイエットに取り組んでいる方も、方向性が合っているかどうかの確認に使って頂ければ幸いです。

30歳 身長170cm 体重70kg の中肉中背
デスクワークのため活動レベルは低い
5キロのダイエットがしたい
例:2ヶ月で5キロ痩せる
- STEP1基礎代謝・総消費カロリーを計算
基礎代謝量 = 1555kcal
総エネルギー消費量 = 2332kcal
計算ツールはこちら - STEP2目標体重(減量kg)までのカロリーを計算
5.0kg × 7200kcal = 36000kcal
36000kcalマイナスにすれば5キロ減る
※脂肪1kg = 約7200kcal - STEP3減量期間を決めて日割り
2ヶ月で5kg減らしたい
36000 ÷ 60 = 600kcal/日
1日600kcalマイナスを60日で5キロ減る - STEP4カロリー収支の式に代入
(摂取カロリー) − (総消費カロリー) = カロリー収支
(摂取カロリー) − (2332kcal) = (−600kcal)
(摂取カロリー) = 1732kcal
1日約1700kcalで生活すれば60日で5キロ減る
摂取カロリーのコントロールのみでダイエットしたい場合はこの計算だけで大丈夫。
筋トレやランニングなどの運動をする日は「総消費カロリー」が増えますので、運動で消費したぶん摂取カロリーを増やして、カロリーがマイナス600kcalになるよう調整します。
カロリーコントロールのコツ・注意点
現実的な減量ペース
減量ペース目安
- 1週間:0.5〜1kg
- 1ヶ月:2〜4kg
- 2ヶ月:4〜8kg
※これくらいが健康的にリスクの少ない減量ペース
体重が多い人(大柄な人)ほど減らせる脂肪のkg数は大きくなりますし、体脂肪が少なかったり小柄な人であれば減らせる幅も小さくなります 。
例えば、もともと体脂肪が10%台前半の人がさらに絞ろうとすると、週に200gとかかなり少ない減量幅になります。
いわゆるぽっちゃり体型、体脂肪が20%(女性は27%)以上くらいの人は週に1kgに近い幅で落とせる と思います。
最低限の摂取カロリー
どんなに早く体重を減らしたくても最低限「基礎代謝量ぶんのカロリー」は摂取してください。
摂取カロリーの幅
- 基礎代謝量:1555kcal
- 総エネルギー消費量 = 2332kcal
- 摂取カロリー:1555〜2332kcalの範囲でダイエットする
これ以上のハイペースでの減量するとリスクがあります。
摂取カロリーが少なすぎるリスク
- 体調不良になる
- 筋肉量の減少
減量で体調不良になるリスク
ハイペースで減量を進めるためには、その分カロリー収支のマイナス幅を大きくする必要があります。
カロリー収支をマイナスにする手段2つ
- 摂取カロリーを減らす(食べない)
- 消費カロリーを増やす(運動する)
例えば週に2kgのハイペースで減量するとしたら、1週間で14000kcalのマイナスをつくることになりますすると、1日あたり2000kcalのマイナスです。これをどうやって実生活でクリアするか。
まず、食事のみでマイナス2000kcalにするとしたら絶食しかありません。一切何も食べなければマイナス2000kcalです。これを1週間続ければ2kgくらい痩せられます。
次に運動で2000kcal消費する場合。
1日2000kcal消費する運動量の目安をあげます。
- ウォーキング:10時間
- 水泳(クロール):2時間
- 水泳(平泳ぎ):4時間
- ジョギング:4時間
- 半身浴:14時間
これを1週間続ければ2kg落ちますが、多分ぶっ倒れます。
こんな感じで、1週間に2kgペースというのは、運動であれ食事制限であれかなり健康的にリスクが高いのでオススメしません。
筋肉が落ちるリスク
マイナスカロリーの生活を続けると基本的には脂肪も筋肉もどちらも落ちますが、極端なハイペースで減量をするほど筋肉が分解されるリスクが高まります。
筋肉が落ちると基礎代謝量が減少し、消費できるカロリーが少なくなります。これが後のダイエットの停滞やリバウンドの原因となります。
ですので、ダイエットはなるべく筋肉量はキープして、脂肪だけをうまく削っていくのがベターです。
それが可能なのが、上に書いた健康的に痩せられる減量ペース(最低限のカロリーは摂取する)ということ。
筋トレ・バルクアップ時のカロリー
筋肉を大きくして体重を増やしたい場合は、摂取カロリーを総消費カロリーより多くしてカロリー収支がプラスになるようにします。
極端に摂取カロリーを増やすと、筋肉より先に脂肪だけ増えてしまいますので、体の変化を見ながら適度にカロリーコントロールをします。
増量時の摂取カロリー目安
- 総消費カロリー+10〜20%
- 総消費カロリー+500kcal
FAQ
カロリー収支の計算どおりに体重が増減しないことももちろんありますし、カロリー収支理論に否定的な意見も存在します。とはいえ、現代の人類が有する医学・科学知識においては「カロリー理論が当てはまらない理由」が解明できていません。理論通りになる場合もあればならない場合もあるけどよくわからんということ。つまり、人間の体の仕組みが完璧に解明されていないと言っても、自主的にコントロールできる数字は「カロリー」くらいなので、どっちにしろ「カロリー収支」を使うしかないよね。と思ってます。
体重は1日単位で数キロくらいは簡単に変動します。途中、体重変化が予定と違ったとしても、決めたカロリーは絶対に変更しないことが重要です。1日単位の体重変化は無視して計画どおりにカロリー収支をコントロールします。どうしても気になるなら体重計に乗らないのがおすすめ。乗るのは1週間に1度くらいで十分。心配しなくても結果は1ヶ月後に出ます。
基礎代謝・カロリー収支のまとめ
体重を増やしたい or 減らしたい だけであれば、基礎代謝量とカロリー収支だけ知っておけば十分です。
計算で出る数字はあくまでも推測値なので、実際に食事と体重を記録しながら自分専用の数字に修正しながら使って下さい
また、筋トレやフィットネスに取り組んでよりかっこいい体へのボディメイクを目的とするのであれば、摂取カロリーの内訳(PFCバランス)の知識も必要です。
カロリー収支を理解した人は是非PFCバランスのコントロールにも挑戦してみてください。
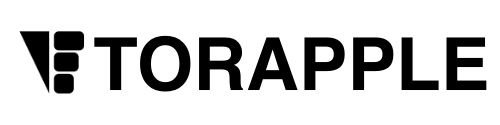




疑問:どの計算式を使えばいいのか?
結論:どれでもいい